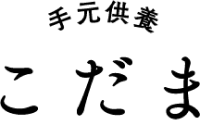手元供養は、大切な方を身近に感じながら供養できる方法です。
近年注目されており、手元供養を検討する方も増えています。
手元供養には多くのメリットがありますが、知っておくべきデメリットも存在します。
本記事では、手元供養のメリット・デメリット、さらには「良くない」といわれる理由について詳しく解説します。
最後まで読むことで、手元供養の良い点と悪い点を把握し、自分に合った供養方法を選べるようになります。
手元供養とは

「手元供養」とは、遺骨の一部もしくはすべてを手元で供養する方法です。
手元供養には遺骨を入れて身に着けられる遺骨ペンダントや、コンパクトなサイズのミニ仏壇などさまざまな種類があります。
手元供養には、分骨と全骨の2種類の供養方法があります。
「分骨」とは、遺骨の一部を手元で供養し、残りはお墓などにおさめる供養方法です。
一方の「全骨」とは、遺骨のすべてを手元で供養します。
分骨と全骨の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
手元供養の全骨とは?分骨との違いややり方、骨壺のサイズについて解説
手元供養の4つのメリット

手元供養のメリットには、下記の4つがあります。
- 故人を身近に感じられ寂しくない
- 居住スペースが狭くて保管しやすい
- 自分好みの手元供養品を選べる
- 一般的なお墓よりも費用をおさえやすい
メリットの内容について、順番に見ていきましょう。
故人を身近に感じられ寂しくない
手元供養を選択すると、遺骨を自宅で保管したり身に着けたりして供養します。
お墓に納骨するわけではないため、故人を身近に感じられます。
「いつも一緒にいたパートナーがいなくて寂しい」と感じている方は、手元供養を検討してみるとよいでしょう。
居住スペースが狭くて保管しやすい
手元供養の分骨を選択すると、遺骨の一部を手元で供養します。
そのため、居住スペースに広さに関係なく保管できる点がメリットです。
自分好みの手元供養品を選べる
手元供養品にはアクセサリーやミニ仏壇、ミニ骨壺など、さまざまな種類があります。
デザインやサイズなどに違いがある手元供養品が多く販売されており、自分好みのものを選択できます。
一般的なお墓よりも費用をおさえやすい
お墓を建てる場合、数百万円ほどの費用がかかるケースは珍しくありません。
高額な費用となるため、金銭的な負担が大きいと感じる方は多くいます。
一方で、手元供養は数万円から数十万程度の費用負担で済むケースもあります。
一般的なお墓を建てるよりも費用をおさえやすく、金銭的な負担を軽減できるのは大きなメリットでしょう。
手元供養の3つのデメリット

手元供養には魅力的なメリットがあります。
しかし、知っておくべきデメリットもあるので、事前に確認しておきましょう。
手元供養のデメリットは、下記の3つです。
- 親族の理解を得られないことがある
- 自分で管理できなくなったときのことを考えておく必要がある
- 紛失する可能性がある
親族の理解を得られないことがある
手元供養が注目されはじめてから、あまり年月が経過していません。
手元供養のことを知らない方からすると「お墓に納骨しないなんて認められない」と、理解を得られないことが考えられます。
親族の理解を得られないのであれば、しっかりと説明して誤解を解くべきです。
手元供養の誤解を解く話し方については、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
手元供養は良くないといわれる理由とは?誤解を解く話し方やメリットを解説
自分で管理できなくなった時のことを考えておく必要がある
手元供養を選択する場合、遺骨や遺灰を供養するのは自分自身です。
健康であれば問題ないですが、病気などにより自分で供養ができなくなった場合、対処法を考えておかなければなりません。
遺族に迷惑がかからないよう、万が一のことを考えた供養方法を決めておきましょう。
また、関係者に共有しておくことも忘れないようにしてください。
紛失する可能性がある
手元供養品は、コンパクトで場所をとらずに保管できる点がメリットです。
しかし、遺骨ペンダントのように小さな手元供養品を選ぶと、紛失リスクが高まります。
遺骨ペンダントを外す際は、あらかじめ決めておいた保管場所に置くようにすれば紛失リスク対策となります。
手元供養が良くないといわれる理由

手元供養が良くないといわれる理由には、下記の4つがあります。
- お墓に納骨しないので縁起が悪いと思われている
- 法律に違反していると考えられている
- お墓に納骨しなければ成仏できないと思われている
- 何となく手元供養は良くないと思い込んでいる
お釈迦さまが亡くなった際、8人の弟子が分骨したといわれています。
また、仏教において手元供養は縁起が悪いものではないので、特に問題はありません。
遺骨の埋葬に関する法律である「墓地、埋葬等に関する法律」では、手元供養に関する内容を定めていません。
そのため、法律に違反していることはなく、安心して供養できます。
そのほかには、手元供養に対して正しく理解していないがために「良くない」と思い込んでいるケースもあります。
ただ、良くないと思われているのは思い込みやイメージであるため、特に気にすることはないでしょう。
手元供養で残った遺骨の供養方法

手元供養で残った遺骨は、適切な方法で供養する必要があります。
ここからは、手元供養で残った遺骨の供養方法を4つ紹介していきます。
- お墓に納骨する
- 散骨する
- 納骨堂に納骨する
- 樹木葬を選択する
お墓に納骨する
先祖代々のお墓にそのまま納骨する供養方法です。
手元供養用の遺骨を分けておき、残りをお墓に納骨します。
ただし、この供養方法はすでにお墓がある方のみが選択できるため、万人向けではありません。
お墓がなければ、そのほかの供養方法を検討しましょう。
散骨する
「散骨」とは、海や山などに遺骨を撒いて供養する方法です。
散骨をする際は、事前に遺骨をパウダー状にしておきます。
また、散骨できない場所もあるので、必ず確認してからおこなうようにしてください。
納骨堂に納骨する
「納骨堂」とは屋内にある遺骨を収蔵する施設で、骨壺のままおさめます。
納骨堂は比較的費用が安く、コストをかけずに供養ができる点がメリットです。
また、屋根がついており、天候に左右されずにお参りできます。
樹木葬を選択する
「樹木葬」とは、樹木や草花をシンボルとした埋葬方法です。
「亡くなったあとは自然に還りたい」と願う方に選ばれています。
樹木葬は永代供養するケースがほとんどなので、承継者が不要です。
埋葬後の管理をお任せできるため、もしものことを考えなくても供養を続けられる点が魅力的です。
まとめ:手元供養のメリットとデメリットを比較して適切な供養方法を選択しましょう

手元供養のメリットとデメリットはこちらです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・故人を身近に感じられ寂しくない ・居住スペースが狭くて保管しやすい ・自分好みの手元供養品を選べる ・一般的なお墓よりも費用をおさえやすい | ・親族の理解を得られないことがある ・自分で管理できなくなったときのことを考えておく必要がある ・紛失する可能性がある |
メリットとデメリットを比較すれば、手元供養が自分に合っている供養方法なのかが分かるようになります。
本記事で解説した内容を参考にして、手元供養を検討してみてはいかがでしょうか。