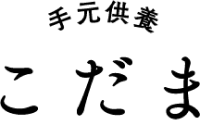手元供養では、故人の遺骨をさまざまな形に加工することで、日常生活の中で故人を身近に感じることができます。
とはいえ、「どのような加工方法があるのか」「加工手順はどうすればよいのか」など、分からないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、手元供養における遺骨加工の方法を詳しく解説し、一般的な加工手順や注意点についてもご紹介します。
手元供養を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも遺骨を加工する手元供養とは?

遺骨を加工する手元供養とは、故人の遺骨やその一部を、特殊な技術を用いてプレートやオブジェ、アクセサリーなどの形に加工し、身近に置いて供養する方法です。
骨壷のまま自宅に置くことに抵抗がある方や、「もっと故人らしい、美しい形で偲びたい」「オブジェのようにリビングに飾りたい」と願う方に選ばれています。
遺骨を加工することで、世界にひとつだけのメモリアル品として生まれ変わり、手に触れて語りかけられるような温かみを感じることができます。
手元供養における加工方法6選

手元供養における遺骨加工には、多様な方法があります。
ここでは、代表的な6つの加工方法について詳しく解説していきます。
- 粉末加工
- ミニ骨壺への収納
- 遺骨ペンダント、アクセサリー加工
- 遺骨ダイヤモンド
- ダイヤモンド以外の宝石加工
- 遺骨プレート、オブジェ
粉末加工
最も一般的で手軽な加工方法が「粉末加工」です。
遺骨を細かいパウダー状にすることで、さまざまな容器に収納しやすくなります。
この方法のメリットは、費用が比較的安価で済むことや、体積が大幅に減ることなどが挙げられます。
一方でデメリットとしては、見た目が大きく変わってしまうため、抵抗を感じる方がいる点です。
また、一度粉末にしてしまうと元に戻すことはできません。
ミニ骨壺への収納
粉末加工した遺骨を小さな骨壺に収納する方法があります。
「ミニ骨壺」とは、従来の骨壺を小型化したもので、自宅の仏壇や専用の安置スペースに置くことができます。
素材には、陶器製・金属製・木製などさまざまな種類があり、価格帯も数千円から数十万円と幅広く、デザインも伝統的なものからモダンなものまで豊富に揃っています。
ミニ骨壺を選ぶ際は、安置場所の雰囲気に合ったデザイン、湿気に強い素材かどうか、将来的に移動しやすいかなどを考慮することが大切です。
遺骨ペンダント・アクセサリー加工
遺骨の一部をペンダントやリング、ブレスレットなどのアクセサリーに加工する方法です。
手元供養品として身に着けることで、いつでも故人と共にいるような感覚を得ることができます。
遺骨アクセサリーには、ステンレス製・チタン製・金や銀製などさまざまな素材があります。
中でも人気が高いのはステンレス製で、錆びにくく、金属アレルギーを起こしにくいのが特徴です。
高級感を重視する方には、金やプラチナ製を選ぶケースも多く見られます。
遺骨アクセサリーを身に着ける際は、激しい運動や水仕事のときには外すことをおすすめします。
また、空港などの金属探知機に反応する可能性があるため、旅行時には注意が必要です。
遺骨ダイヤモンド
遺骨に含まれる微量の炭素を抽出し、他の炭素源と組み合わせて人工的にダイヤモンドを生成する方法です。
科学技術の進歩により、天然ダイヤモンドと遜色ない美しさと硬度を持つダイヤモンドを作ることが可能になりました。
遺骨ダイヤモンドの費用は数十万円から数百万円と高額ですが、半永久的に保存でき、世代を超えて受け継ぐことができるという点が大きなメリットです。
ダイヤモンド以外の宝石加工
近年では、ダイヤモンド以外の宝石への加工にも注目が集まっています。
故人の個性や好みに合わせて素材を選べる点が大きな魅力です。
「麗石(れいせき)」は、遺骨を原料として作られる人工石で、天然石のような美しい色合いと光沢を持っています。
硬度が高く、日常的に身に着けても傷がつきにくいのが特徴です。
色は故人のイメージに合わせて選ぶことができ、複数個の作成も可能です。
「遺骨真珠」は、遺骨の一部を核として育てられる真珠で、自然な光沢と気品ある美しさを備えています。
特に女性からの人気が高く、ネックレスやイヤリングなどへの加工が可能です。
真珠ならではの上品な輝きは、多くの方に長く愛されています。
遺骨プレート・オブジェ
遺骨を混ぜ込んで作るプレートやオブジェも、人気のある加工方法のひとつです。
芸術的な要素を取り入れることで、故人の個性や想いを形にすることができます。
遺骨を陶器やガラスに混ぜ込み、花瓶や置物、プレートなどに加工します。
陶芸作家やガラス作家との協力により、世界にひとつだけのオリジナル作品を作ることが可能です。
金属プレート加工では、主にステンレスやチタンが使用され、耐久性やデザイン性に優れています。
一部では金や銀を使用する例もありますが、非常に高価になるため、事前に費用や仕様を確認しておくと安心です。
遺骨の加工方法の選び方

後悔しないためにも、下記のポイントを確認してから遺骨の加工方法を選ぶようにしましょう。
- 予算を決めておく
- 将来の管理や承継を考慮する
予算を決めておく
手元供養の加工方法を選ぶ際に、まず考慮すべきなのは予算です。
たとえば、粉末加工やミニ骨壺であれば、比較的低予算で対応できますが、遺骨ダイヤモンドのような加工は高額になる可能性があります。
また、予算を立てる際には初期費用だけでなく、将来的な維持管理費も視野に入れて検討することが大切です。
将来の管理や承継を考慮する
手元供養を始める際には、将来的な管理や次世代への承継についても考慮する必要があります。
管理のしやすさや、子どもや孫など家族に理解・受け入れてもらいやすい形態であるかどうかを確認しておくことが大切です。
長期的な視点から、家族全体にとって最適な選択を心がけましょう。
遺骨を加工する手順

依頼から完成までの一般的な流れを、4つのステップで紹介します。
- Step1.関係者で話し合い加工方法を決める
- Step2.業者を選び問い合わせ・相談する
- Step3.遺骨を業者に送る
- Step4.完成・受け取り
Step1.関係者で話し合い加工方法を決める
まずは、関係者全員が納得できるよう、しっかりと話し合いを行いましょう。
それぞれの加工方法のメリット・デメリットを理解したうえで、「故人らしさが感じられるのはどの方法か」「自分たちのライフスタイルに合っているか」をじっくりと検討することが大切です。
Step2.業者を選び問い合わせ・相談する
加工方法が決まったら、それに対応している専門業者を探しましょう。
Webサイトで実績や制作例、費用などを確認し、気になる業者には複数問い合わせて比較検討するのがおすすめです。
また、電話やメールでの対応の丁寧さも、その業者が信頼できるかどうかを見極める大切なポイントとなります。
Step3.遺骨を業者に送る
依頼する業者が決まったら、契約を交わし、遺骨を送付します。
送骨に対応している業者の中には、遺骨を安全に送るための「送骨キット」を用意している場合もあります。
利用可能かどうか、事前に確認しておくと安心です。
加工方法によっては、あらかじめ遺骨を粉末状にする「粉骨(ふんこつ)」が必要な場合もありますが、多くの業者がこの作業も含めて対応しています。
Step4.完成・受け取り
制作期間を経て、完成したメモリアル品が手元に届きます。
故人が新しい形となって帰ってくるのを待つ時間もまた、故人を想う大切な供養の時間となるでしょう。
手元供養のために遺骨を加工する際の3つの注意点

大切な遺骨を預けるからこそ、後悔のない選択をするために、事前に知っておくべき注意点があります。
加工を始める前に、以下の点を必ず確認しておきましょう。
- 加工する遺骨の量はどのくらいか
- 一度加工すると元の形には戻せない
- 信頼できる業者を選ぶ
加工する遺骨の量はどのくらいか
一般的には、遺骨の一部のみを使用して加工する方法が主流です。
ただし、中には手元にある遺骨の大半を加工に用いる方もいらっしゃいます。
どの程度の量を使用するか、また、加工に使わなかった遺骨を今後どのように供養するかについても、あらかじめしっかり考えておくことが大切です。
一度加工すると元の形には戻せない
言うまでもありませんが、一度加工した遺骨は、元の状態に戻すことはできません。
だからこそ、遺骨を加工するという決断は、慎重に行うことが何より大切です。
ご夫婦だけでなく、ご両親やきょうだいなど、関係の深いご親族とも相談し、できるだけ多くの方が納得できる形を選ぶことが望ましいでしょう。
信頼できる業者を選ぶ
大切な遺骨を預ける以上、業者選びは非常に重要です。
以下の点を事前にしっかり確認しましょう。
- 豊富な実績があるか
ホームページなどで、制作事例や過去の実績を多数公開しているかを確認しましょう。 - 費用が明確か
基本料金だけでなく、オプション費用や追加料金についても、事前に明確な説明があるかを確認します。 - 対応が丁寧か
問い合わせや相談時に、親身で分かりやすい説明をしてくれるかどうかは重要な判断材料です。 - 遺骨の管理体制が整っているか
遺骨の受け取りから保管、加工まで、どのような管理体制で扱われるのか説明があるかを確認しましょう。
まとめ:遺骨を手元供養品に加工すれば故人との絆を形にできる

遺骨を加工する手元供養は、決して「故人をモノに変える」行為ではありません。
遺骨を新たな形にすることで、故人との大切な思い出や絆が「目に見えるかたち」となり、これからの人生に静かに寄り添ってくれる存在となります。
大切なのは、費用や見た目だけでなく、故人への想いを大切にし、ご家族の絆をより深められる方法を選ぶことです。
また、手元供養を始めるタイミングに決まりはありません。
故人を失った悲しみのなかで、すぐに決断する必要はありません。心が落ち着き、ご自身やご家族の気持ちに整理がついたときに、ゆっくりと検討しても遅くはないのです。
ご夫婦やご家族でじっくり話し合い、ときには専門家の意見も参考にしながら、悔いのない選択をされることをおすすめします。