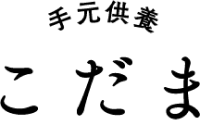少子高齢化が進む現代では、従来のお墓を承継し維持していくことが困難な家庭が増えています。
墓石の購入費用や年間管理料の負担など、さまざまな課題を抱える中で、新しい供養の形が注目を集めています。
手元供養や散骨、分骨などの選択肢から、それぞれの特徴や必要な手続きを理解し、自分や家族に最適な供養方法を選択することが重要です。
本記事では、お墓を持たない新しい供養方法として、手元供養と散骨・分骨・納骨の違いを解説します。
自分や家族が納得できる供養の選び方や手続きについて知りたい方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
手元供養とは

まずは、手元供養についての理解を深めていきましょう。
- 墓じまいやお墓を持たない背景
- 手元供養のメリット・デメリット
墓じまいやお墓を持たない背景
従来、日本では家のお墓に遺骨を納めるのが一般的でした。
しかし、核家族化や少子化の影響で、お墓を継ぐ人がいないという問題が深刻化しています。
さらに、供養の考え方の変化により、従来型のお墓にとらわれない新しい供養方法が注目されるようになりました。
その中でも手元供養は、自宅に遺骨や遺灰の一部を安置する方法で、故人を身近に感じられる点が大きな魅力です。
手元供養のメリット・デメリット
手元供養の最大のメリットは、日常の中で故人を偲ぶことができる点です。
ミニ骨壺や遺骨ペンダントを用いれば、外出先でも供養が可能になります。
一方で、遺骨の保管には湿気対策が必要であったり、家族間の価値観の違いがトラブルを生む可能性もあります。
手元供養を選ぶ際は、これらの点を理解しておくことが重要です。
散骨・分骨・納骨の違いを理解する

散骨や分骨、納骨は、それぞれ供養の形が異なります。
違いを理解することで、自分や家族に合った供養方法を選びやすくなります。
- 散骨とは
- 分骨とは
- 納骨とは
散骨とは
散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山などに撒く供養方法です。
墓地に納めず自然に還すことが特徴で、永続的なお墓の維持が不要です。自宅に遺骨を置いて供養する手元供養とは、真逆の考え方といえます。
法律上、散骨には明確な許可制度は設けられていませんが、他人の所有地や公共の場所では許可が必要な場合があります。
また、自治体によっては禁止区域があったり、無断で山林に撒くとトラブルになることもあります。
専門業者に依頼すれば、適切に散骨を行ってくれるため安心です。
分骨とは
分骨とは、遺骨を複数の場所で供養する方法です。
家族が遠方に住んでいる場合や、寺院と自宅の両方で供養したいときなどに選ばれます。
分骨の一部を手元供養に使うケースも多く、両者を組み合わせて活用できる点が特徴です。
分骨を行う際は、「分骨証明書」が必要になることがあります。分骨証明書は火葬場や墓地管理者が発行する書類で、後々のトラブル防止にもなるため、必ず確認しましょう。
分骨について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
手元供養の分骨は自分でできる?方法やタイミング、注意点について解説
納骨とは
納骨は、遺骨を墓地や納骨堂に納める伝統的な供養方法です。
多くの場合、宗教儀式を伴い、家族や親族が集まって行われます。
納骨は寺院や墓地に遺骨を預けるのに対し、手元供養は自宅に置いて日常的に供養できる点が異なります。
墓じまいとは

墓じまいとは、既存のお墓を撤去し、遺骨を取り出すことを指します。
少子化によってお墓の承継者がいない場合や、遠方で管理が困難なときに選ばれることが多いです。
- 墓じまいが選ばれる理由
- 取り出した遺骨の扱い方
墓じまいが選ばれる理由
墓じまいが選ばれる理由には、経済的な負担、遠方居住による管理の困難さ、宗教観の変化などが挙げられます。
核家族化が進む現代では、こうした背景から現実的な選択肢として注目されています。
取り出した遺骨の扱い方
墓じまい後の遺骨は、永代供養墓への改葬、手元供養、散骨など、さまざまな方法で供養することができます。
また、多くの場合は一つに限らず、複数の方法を組み合わせて供養されることもあります。
必要な手続きと書類|分骨証明書・埋葬許可証・改葬許可証の取得方法

手元供養や散骨、分骨を行う際には、法的に定められた書類の準備が必要です。
代表的なものに、分骨証明書や埋葬許可証、そして改葬許可証があります。これらの書類がどのような場面で必要になるのか、取得方法とあわせて解説します。
- 分骨証明書とは
- 埋葬許可証とは
- 改葬許可証とは
分骨証明書とは
分骨証明書は、遺骨の一部を別の墓地等に納骨する際に必要な書類です。
手元供養をする場合は、新しい納骨先がないため、分骨証明書を提出する必要はありません。
ただし、遺骨を取り出す際に墓地管理者から発行を求められることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
火葬場で発行する分骨証明書
火葬時に分骨を行う場合は、火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。
その際には、あらかじめ分骨の予定があることを火葬場に伝えておく必要があります。
また、事前に分骨用の骨壷も準備しておきましょう。
墓地管理者が発行する分骨証明書
すでに納骨されている遺骨を分骨する場合は、寺院や霊園などの墓地管理者から分骨証明書を発行してもらいます。
その際、僧侶による閉眼供養が必要になることもあります。
手元供養時の分骨証明書の要否
手元供養のみを目的とする分骨の場合、分骨証明書は必ずしも必要ありません。
しかし、将来的に納骨する可能性を考えると、あらかじめ取得しておくことをおすすめします。
埋葬許可証とは
埋葬許可証は、遺骨を墓地に納骨する際に必要な書類です。
市区町村が発行する火葬許可証に、火葬場が火葬済みであることを示す証明印を押したものを指します。
火葬許可証との違い
火葬許可証は、火葬を行うために必要な書類で、火葬後には埋葬許可証としての役割も果たします。
この書類がなければ、遺骨をどこにも納骨することはできません。
埋葬許可証が必要なケース
改葬許可証は、手元供養していた遺骨を将来的に納骨する場合や、墓じまい後にほかの墓地へ改葬する際に必要となる書類です。
紛失した場合は、火葬を行った市区町村役場で再発行の手続きを行います。
改葬許可証とは
墓じまいを行い、遺骨を別の墓地へ移す場合には、改葬許可証が必要です。
市区町村での申請方法
改葬を行う場合は、現在のお墓がある市区町村に改葬許可申請書を提出します。
この際、埋葬証明書や受入証明書、改葬理由書などの書類が必要です。
必要書類と注意点
申請には、現在の墓地管理者の署名・押印や、新しい納骨先の受入証明書が必要です。
また、手続きには時間を要するため、余裕を持って準備することが大切です。
手続きの実践ガイド|ケース別の進め方

実際に手元供養や分骨を行う際の手続きを、ケースごとに整理して解説します。
状況に応じた進め方を確認しましょう。
- 火葬時から分骨する場合の手続き
- 納骨後に分骨する場合の手続き
- 墓じまい後の遺骨の扱い方
火葬時から分骨する場合の手続き
火葬前に分骨の意思を火葬場に伝え、分骨用の骨壷を準備します。
火葬後、分骨証明書の発行を受け、それぞれの納骨先で手続きを行います。
事前準備と火葬場での対応
分骨時に必要な準備としては、分骨用骨壷の購入、火葬場への事前連絡、そして分骨証明書の発行依頼があります。
また、火葬場によっては追加料金が発生する場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
複数箇所への納骨時の注意点
複数の墓地に納骨する場合は、それぞれの納骨先で分骨証明書が必要です。
また、納骨先の宗派や規則によって手続きが異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。
納骨後に分骨する場合の手続き
既に納骨されている遺骨を分骨する場合は、墓地管理者との調整が重要です。
墓地管理者との調整
分骨を行う際は、理由や時期、方法について墓地管理者と相談する必要があります。
特に寺院墓地の場合は、住職との十分な話し合いが求められます。
僧侶による閉眼供養
遺骨を取り出す前には、僧侶による閉眼供養(魂抜き)を行うのが一般的です。
閉眼供養を経ることで、遺骨を安心して取り出すことができます。
墓じまい後の遺骨の扱い方
墓じまいで取り出した遺骨には、永代供養への改葬や手元供養、散骨など、さまざまな選択肢があります。
それぞれの特徴と手続きの流れを理解したうえで、自分や家族にとって最適な方法を選びましょう。
永代供養への改葬
永代供養墓への改葬は、将来的な管理の負担がない方法として近年人気を集めています。
永代供養墓には、合祀型と個別型があり、それぞれで費用や供養方法が異なります。
手元供養と合祀の組み合わせ
遺骨の一部を手元供養し、残りを合祀墓に納骨する方法を選ぶこともできます。
この場合は、分骨証明書の取得が必要です。
まとめ:故人の意思と家族の思いを尊重できる供養方法を選び、納得できる供養をしましょう

お墓を持たない新しい供養方法は、現代のライフスタイルや価値観に合った選択肢として、近年広く受け入れられています。
手元供養や散骨、分骨といった方法を組み合わせることで、故人への想いを大切にしながら、最適な供養の形を見つけることができます。
供養方法を選ぶ際には、家族の理解・将来の管理方法・宗教的な配慮などを総合的に検討することが大切です。
また、分骨証明書や埋葬許可証といった法的な手続きも必要になるため、専門家のアドバイスを受けながら準備を進めると安心です。