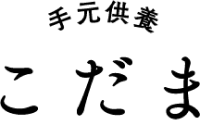遺骨の一部を自宅で供養する手元供養が注目されています。手元供養を選択すると、自宅で遺骨を供養することとなります。そのため、遺骨の一部を手元供養品の中に入れる分骨をおこなうのが一般的です。
「分骨を自分でできるのか」という悩みを抱えている方がいるでしょう。そこでこの記事では、手元供養の分骨は自分でできるのか、という疑問について回答していきます。
また、分骨の方法やタイミング、注意点についても解説していくので、手元供養を検討している方はぜひ最後まで目を通してみてください。
分骨とは

「分骨」とは、故人の遺骨を複数箇所に分けて埋葬もしくは供養することです。故人を供養する場合、お墓に埋葬する方法が一般的だと考えている方が多いです。
しかし、分骨をすれば故人の遺骨を手元で供養できます。
分骨は自分でできるのか

結論からお伝えすると、分骨は自分でできます。ただし、分骨をするタイミングによっては、さまざまな手続きが発生する可能性があります。
そのため、分骨のタイミングを図ることが重要です。
自分で分骨する方法とタイミング

自分で分骨する方法は、タイミングによって異なります。自分で分骨する場合のタイミングには、下記の3つがあります。
- 火葬のときに分骨する
- 納骨前の自宅安置期間中に分骨する
- 納骨後に分骨する
それぞれのタイミングについて、順番に見ていきましょう。
火葬のときに分骨する
火葬時に分骨する場合は、火葬後の骨上げのタイミングが最適です。事前に葬儀社や火葬場のスタッフに分骨をする旨を伝えておけば、スムーズに分骨できます。
また、分骨用の骨壺を用意しておくと、煩雑な手続きをすることなく分骨できます。
納骨前の自宅安置期間中に分骨する
故人の遺骨を骨壺におさめておき、納骨前の自宅安置期間に分骨するケースです。分骨用の骨壺を用意しておけば、霊園やお寺の許可を得ることなく自分で分骨できます。
納骨後に分骨する
納骨後に分骨することも可能ですが、墓地管理者の許可が必要です。墓地管理者の許可を得たあとはお墓の蓋を開け、骨壺を取り出します。
お墓の蓋は非常に重く、取り扱いがむずかしいため、石材店に作業を依頼するとよいでしょう。このように、納骨後の分骨は手続きが増えてしまいます。
分骨の手続きを少なくしたい方は、ほかのタイミングで分骨しましょう。
自分で分骨する際の注意点
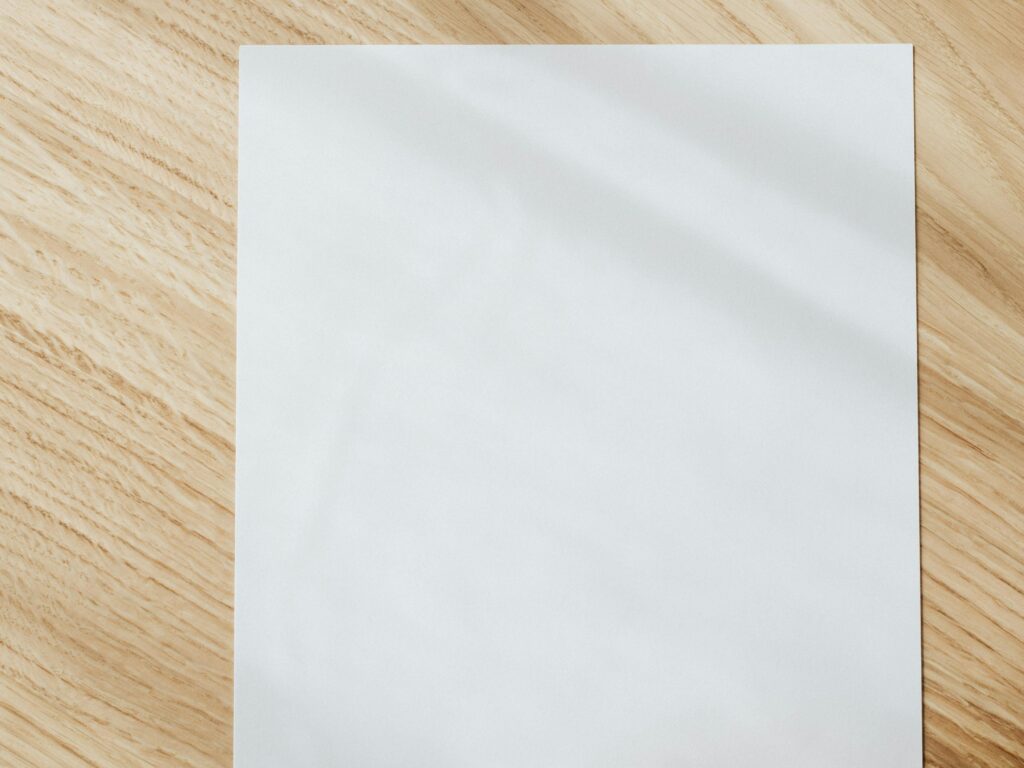
自分で分骨する際は、下記の3つのポイントに注意しておきましょう。
- 家族や親族の同意を得ておく
- 分骨証明書を用意しておく
- カビを発生させないように気をつける
ひとつずつ解説していきます。
家族や親族の同意を得ておく
手元供養が注目されはじめたのは最近です。そのため、手元供養についてよく理解していない家族が親族がいる可能性があります。
家族や親族の同意を得ないまま分骨してしまうと、のちのちトラブルとなってしまうかもしれません。分骨に理解を得られるように、事前に説明して同意を得ておきましょう。
分骨証明書を用意しておく
分骨した遺骨を埋葬する際は「分骨証明書」が必要です。分骨証明書は、納骨先の墓地管理者に依頼することで発行してもらえます。
カビを発生させないように気をつける
自分で分骨する際、遺骨を素手で触ってしまうとカビが生えてしまう可能性があります。自分で分骨をする場合は、ゴム手袋をはめる、箸を使うなどして直接遺骨を触らないように注意しましょう。
分骨後の手元供養方法

分骨したあとに手元供養する際は、ミニ骨壺やミニ仏壇、遺骨アクセサリーなどがあります。自分に合う供養方法を選択するようにしましょう。
まとめ

手元供養の分骨は自分でできます。ただし、分骨するタイミングによって、手続きが発生するケースがあります。
自分で分骨するタイミングは、下記の3つです。
- 火葬のときに分骨する
- 納骨前の自宅安置期間中に分骨する
- 納骨後に分骨する
また、自分で分骨する際は、下記の3つのポイントに注意してください。
- 家族や親族の同意を得ておく
- 分骨証明書を用意しておく
- カビを発生させないように気をつける
手元供養の分骨を自分でしたいと考えている方は、この記事で解説した内容を参考にしてみてください。