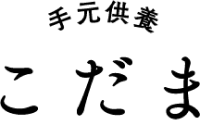従来のお墓参りとは違い、手元供養は故人をより身近に感じられる点が評価され、多くの人に注目されています。
しかし、見落としがちな問題点も存在します。
手元供養を始めてから「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、あらかじめ潜在的な問題点を把握し、適切な対処法を知っておくことが大切です。
本記事では、手元供養の問題点と解決策、起こり得るトラブル事例などを詳しく解説します。
手元供養の問題点とその対処法を事前に把握し、安心して自分たちらしい供養をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
手元供養の7つの問題点と解決策

手元供養には多くのメリットがある一方で、実際に始めてから直面する問題点も存在します。
ここからは、事前に知っておくべき7つの問題点とその解決策について、詳しく解説していきます。
- 家族や親族の理解が得られない場合がある
- 遺骨の保管に関する法的・宗教的な懸念がある
- 将来的な承継について考えておく必要がある
- 心理的負担や罪悪感を感じるケースがある
- 手作り品の耐久性や品質に注意が必要
- 引越しや災害時のリスクがある
- 最終的な納骨先の確保が困難になることがある
家族や親族の理解が得られない場合がある
手元供養は、まだ一般的な認知度が十分に浸透しているとはいえません。
特に高齢世代や伝統的な価値観を持つ親族の中には、違和感や拒否反応を示す方もいます。
たとえば、年配の親族から「お墓に納めてこそ供養だ」「家に骨を置くのは縁起が悪い」といった意見が出ることも珍しくありません。
また、仏教をはじめとする宗教的な伝統が強く残る家庭では、手元供養を“供養の省略”と受け取られ、宗教的・精神的に違和感を覚える方もいます。
特に、菩提寺とのつながりが深い家庭では、僧侶の理解を得る必要があり、場合によっては宗教儀礼や法要の実施が難しくなることもあります。
そのため、手元供養を始める際には、事前に家族や親戚と十分に話し合い、理解を得ることがトラブルを避ける鍵となります。
遺骨の保管に関する法的・宗教的な懸念がある
日本では、火葬後の遺骨の取り扱いについて明確な規定がある一方、自宅での一時保管を明確に禁止する法律は存在していません。
ただし、遺骨の扱いには節度ある保管が求められており、公共性のある場所での放置や不適切な扱いは遺骨遺棄とみなされ、刑事罰の対象となる可能性があります。
また、宗教的な視点から見ると、遺骨はしかるべき供養の場(墓地や納骨堂)に納めるべきという考え方が根強くあります。
特に仏教の一部宗派では、「遺骨を家に置くことで魂が成仏できない」とされることもあり、手元供養を選ぶこと自体が、菩提寺や寺院との関係を悪化させる要因になりかねません。
手元供養を選択する場合は、宗教的な観点と法的リスクの両面を理解したうえで、節度ある保管と供養の形を考えることが大切です。
将来的な承継について考えておく必要がある
手元供養は、今この瞬間の心のケアには適していても、長期的な視点では課題が残ります。
その課題のひとつが、承継問題です。
たとえば、子どもがいない場合や、いても供養自体に関心がない場合、故人の遺骨が将来的に放置される可能性があります。
また、ライフスタイルや価値観が多様化する中で、子どもや孫世代が手元供養を続ける責任を感じにくいことも問題点です。
さらに、転勤や海外移住などの事情により、遺骨の引き継ぎが物理的に困難となるケースも考えられます。
こうした背景から、手元供養を選ぶ場合でも、いずれは納骨する・散骨を検討するなど、終活の一環として最終的な供養の形を明確にしておくことが重要です。
心理的負担や罪悪感を感じるケースがある
手元供養は、「いつでも会える」という安心感を与えてくれる反面、故人を手放せないことで心の整理がつかず、グリーフ(悲嘆)から抜け出せないという側面もあります。
グリーフケアの観点では、故人との適度な距離を保ち、悲しみから前向きに生きる力を取り戻すことが大切とされており、手元供養がそれを阻害するリスクも否定できません。
こうした心の動きにも目を向け、必要であれば専門家に相談することも一つの手段です。
手作り品の耐久性や品質に注意が必要
最近では、手元供養品を手作りでDIYする方も増えています。
木工や陶芸、手芸などでオリジナルの仏壇や骨壺を作ることで、より故人に合った温かみのある供養が可能になります。
しかし一方で、耐久性に関する問題が見過ごされがちです。
手作りの骨壺や供養台は、プロの製品と比べて密閉性や湿気対策が十分でないことが多く、時間が経つとヒビ割れや変形、カビの発生といったリスクが高まります。
もし手作りを希望する場合は、防湿対策を講じたり、強度を確保できる素材を選んだりする工夫が求められます。
関連記事はこちらです。
手元供養品は手作りできる?心のこもった供養品の種類と作り方、注意点を解説
引越しや災害時のリスクがある
手元供養は自宅でおこなうため、引っ越しや災害といった予期せぬ事態に備える必要があります。
たとえば、転居の際には遺骨を慎重に運ぶ必要があり、壊れやすい骨壺や手元供養品が破損するリスクも高まります。
また、賃貸住宅では、契約条項によっては遺骨の保管について事前に相談が必要な場合があり、トラブルが発生する可能性もゼロではありません。
さらに、地震や火災、水害などの災害発生時には、遺骨の保護が難しく、紛失や損傷のおそれがあります。
そのため、専用の耐火ケースや耐震固定、保険の活用など、物理的リスクへの備えも検討すべきでしょう。
最終的な納骨先の確保が困難になることがある
法律上、手元供養をいつまでも続けることは可能ですが、将来的には相続や住宅事情などから納骨先を検討する必要が出てくる場合もあります。
もしものことを考え、あらかじめ遺骨の納め先を決めておくことが望ましいでしょう。
しかし、現代では墓地不足や高額な納骨費用の問題があり、適切な納骨先を見つけるのが難しいケースもあります。
特に都市部では、納骨堂が満員だったり、永代供養の費用が想定より高額だったりすることも珍しくありません。
また、散骨を希望しても家族が反対する、宗教上の理由で難しいといった問題に直面することも考えられます。
早めに家族と方針を共有し、具体的な手続きを調べておくことが求められます。
手元供養で起こり得るトラブル事例

ここからは、手元供養で起こり得るトラブル事例を紹介していきます。
事前にトラブル事例を知ることで、同様の失敗を避けられるようになります。
- 家族間で意見が対立することがある
- 誤った保管方法を選択してしまうことがある
- 手作り品の破損や劣化が発生することがある
家族間で意見が対立することがある
「母の遺骨を手元に置きたい」と考える方と「きちんとお墓に納めるべき」と主張する方の間で、激しい対立が生じる可能性があります。
結果的に家族関係が悪化し、供養どころか遺族間の絆が損なわれるケースも考えられます。
誤った保管方法を選択してしまうことがある
湿気の多い場所に骨壺を置いた結果、カビが発生したり、ペットが骨壺を倒して遺骨が散乱したりする事故が発生しています。
また、手作りの木製骨壺が虫害を受けるトラブルも報告されています。
手作り品の破損や劣化が発生することがある
陶芸で作成した手作り骨壺にひびが入り、遺骨が湿気にさらされる事例があります。
また、手作り仏壇の塗装が剥がれて、見た目が損なわれるトラブルが報告されています。
手元供養が向いている人・向いていない人の特徴

手元供養はすべての方に適した供養方法ではありません。
自分の状況や価値観に照らし合わせて、適性を客観的に判断することが大切です。
- 手元供養が向いている人の特徴
- 手元供養が向いていない人の特徴
手元供養が向いている人の特徴
手元供養が向いている人の特徴はこちらです。
- 故人をいつも身近に感じていたい人
- 宗教儀礼に縛られず、自分らしい供養を望む人
- お墓の維持や移動がむずかしい事情がある人
- 承継者のいない単身世帯や高齢者夫婦
上記の特徴に該当する人にとって、手元供養は非常に柔軟で心の安定にもつながる方法です。
手元供養が向いていない人の特徴
続いて、避けたほうがよい可能性がある人の特徴も見てみましょう。
- 宗教的な決まりを重視している家庭
- 親族や配偶者の理解が得られていない人
- 湿気や環境管理がむずかしい住環境にある人
- 将来的にどうするかを決められない人
トラブルや後悔を避けるために、あらかじめ上記のような不安要素がある場合は、慎重に検討しましょう。
まとめ:手元供養の問題点を把握して適切に対処しましょう

手元供養の問題点は存在しますが、事前の十分な準備と適切な知識があれば、多くの問題は解決可能です。
大切なのは、メリットだけでなくデメリットも含めて総合的に判断し、家族全員が納得できる選択をすることです。
最終的な決断の前に、本記事の内容を家族で共有し、十分な話し合いを重ねてください。
適切な準備と家族の理解があれば、手元供養は故人との絆を深める意義深い供養方法となるでしょう。