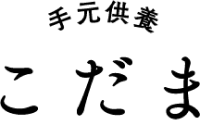近年、注目を集めている供養方法のひとつが手元供養です。
しかし、いざ検討をはじめると「費用はどれくらいかかるの?」「相場や料金の違いは?」と不安になる方も多いでしょう。
本記事では、手元供養にかかる費用や相場から、安くおさえる方法までわかりやすく解説します。
手元供養にかかる費用とは?料金・金額の基本知識

まずは、手元供養にかかる費用の基本を押さえましょう。
手元供養料金の目安や内訳、値段が変動する理由について解説し、納得のいく手元供養の第一歩をサポートします。
- 手元供養の料金・金額の目安
- 手元供養に含まれるおもな費用項目
- 手元供養の値段が変わる理由
手元供養の料金・金額の目安
手元供養にかかる料金は、選ぶアイテムや料金プランによって異なります。
一般的な費用の目安としては、3万円から10万円程度が中心価格帯です。
シンプルなミニ骨壷やミニ仏壇だけなら3万円以内でそろうケースもありますが、オーダーメイドのアクセサリーや高級素材を使ったアイテムは、10万円を超えるケースもあります。
手元供養に含まれるおもな費用項目
手元供養の費用には、さまざまな項目が含まれます。
代表的な費用は骨壷や仏壇、ジュエリーなどの購入費用です。
加えて、遺骨の一部を取り分ける際には分骨証明書の発行手数料や、遺骨を細かく砕く粉骨費用が発生することもあります。
また、郵送で遺骨を送る場合には、送料も別途必要です。
手元供養に必要な費用項目の全体像を把握しておけば、事前に資金を用意できるでしょう。
手元供養の値段が変わる理由
手元供養の値段に幅がある理由は、手元供養品に使用される素材やデザインの自由度によるものです。
たとえば、陶器製のミニ骨壷なら比較的安価ですが、高級木材を使った仏壇や職人の手作業によるオリジナル品となると価格は跳ね上がります。
また、アクセサリータイプではダイヤモンド加工など特殊な技術が使われることもあり、その分コストがかかるケースも考えられます。
ご自身が希望するスタイルに応じた予算設定が重要です。
手元供養の料金相場
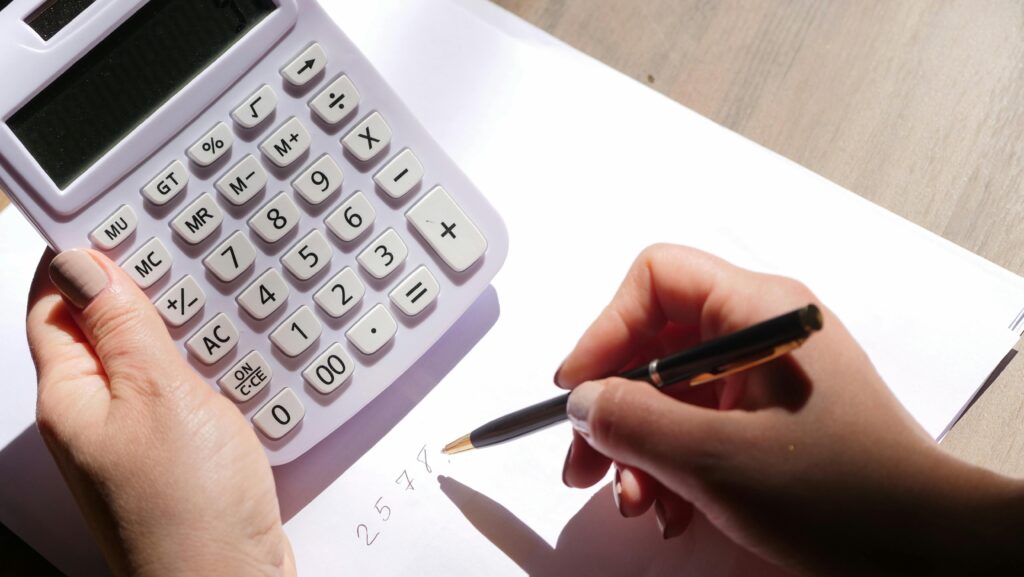
手元供養にもさまざまなスタイルがあり、タイプごとに費用の相場が異なります。
ここからは代表的な手元供養品やオーダーメイド品、さらに100均一を活用する方法まで、タイプ別の料金相場を解説します。
- 代表的な手元供養品の相場と費用例
- オーダーメイド品の相場と費用例
- 手元供養を100均一でそろえることはできるのか
代表的な手元供養品の相場と費用例
代表的な手元供養品には、ミニ骨壺やミニ仏壇などがあります。
それぞれの費用相場をまとめた表がこちらです。
| 手元供養品 | 相場価格帯 | 備考 |
|---|---|---|
| ミニ骨壺 | およそ5,000円~30,000円 | 素材(陶器・ガラス・金属など)やデザインにより幅がある |
| ミニ仏壇 | およそ10,000円~100,000円 | シンプルなものは安価、高級材やオーダーメイド品は高額な傾向がある |
| 遺骨アクセサリー | およそ10,000円~50,000円 | ・遺骨ペンダントや遺骨ネックレスなどがある ・素材(シルバー・ゴールド)によって価格が変動する |
オーダーメイド品の相場と費用例
オーダーメイドで作る手元供養品は、一般的なものに比べて高額となる傾向があります。
費用の目安は10万円から30万円程度です。
たとえば遺骨を入れるアクセサリーは、素材がシルバーなら比較的安く、プラチナやゴールドを使うと値段が上がります。
また、デザインのカスタマイズや刻印サービスなど、オプションを加えるごとに費用も増えていきます。
手元供養を100円均一でそろえることはできるのか
手元供養品を100円均一でそろえ、費用をおさえたいと考える方もいるでしょう。
お店の品ぞろえにもよりますが、小型ケースやシンプルな写真立て、ろうそく立てなどは100円均一でも手に入ります。
しかし、遺骨を入れる容器としての耐久性や密閉性を考えると、専用の手元供養用品を選ぶほうが安心です。
お金の節約は大切ですが、大切な方を供養するための品質は重視しましょう。
手元供養を安くする方法と費用をおさえるコツ

手元供養には、費用をおさえる方法やコツがあります。
下記の2つの方法について解説していきます。
- セット内容を絞る
- 優先順位をつける
セット内容を絞る
費用をおさえるには、まずセット内容を絞ることがポイントです。
たとえば、最初から多くのアイテムをそろえるのではなく、最低限の骨壷とミニ仏壇のみを選び、必要に応じてあとから追加購入する方法があります。
また、通販サイトではアウトレット品や型落ち品が安く販売されていることもあります。
値段の安さだけで決めず、商品の質を選ぶことも大切です。
優先順位をつける
手元供養品は、高品質のものやデザイン性の高いものは高額となる傾向があります。
そこで、手元供養品で何を重視したいのかを決めます。
「デザインは重視したいので、素材にはこだわらない」「コスト面をできるだけおさえたいから、シンプルなデザインの骨壺のみにする」など、譲れる点と譲れない点を整理しておきましょう。
優先順位を明確にしておけば、費用をおさえつつ納得できる手元供養品を選べるようになります。
手元供養と葬儀費用との関係
手元供養は、従来の葬儀に比べて費用面で負担を軽減できるケースがあります。
ここからは、手元供養と葬儀費用との関係について解説していきます。
- 一般的な葬儀費用と手元供養の違い
- 手元供養を選ぶことで節約できるケース
- 後悔しないための費用プランの立て方
一般的な葬儀費用と手元供養の違い
一般的な葬儀費用は、全国平均でおよそ100万円から200万円程度といわれています。
一方、手元供養は3万円から10万円ほどで済むケースが多く、大幅なコストダウンが可能です。
特に、遺骨を手元に置くスタイルはお墓の購入や維持費もかからず、長期的な経済負担もおさえられる点が魅力です。
近年、経済的負担を減らしたいと考える家族から選ばれる理由のひとつとなっています。
手元供養を選ぶことで節約できるケース
たとえば、お墓を建てずに手元供養をする場合、墓石代(100万円以上)が不要となります。
また、納骨堂や永代供養墓を利用する際、手元供養と併用することで規模を小さくできるため、その分のコストカットが可能です。
金銭的に負担の大きい高額な墓地を探さず、自宅で心を込めて供養できるスタイルは、経済的にも精神的にも負担の少ない選択肢といえるでしょう。
後悔しないための費用プランの立て方
手元供養を選ぶ際は、初期費用だけでなく、今後の維持管理コストも視野に入れてプランを立てることが大切です。
たとえば、将来的に移動や管理が難しくなった場合を想定して、改葬先や合祀先などを決めておくと安心です。
あらかじめ家族とも相談し「いくらまでなら無理なく支払えるか」というラインを決めておくと、後悔のない選択ができます。
まとめ:手元供養の費用を理解して納得できる供養をしましょう

手元供養は、従来の供養方法に比べて費用をおさえながら、大切な人を身近に感じられる新しいスタイルです。
料金の相場や費用の内訳をしっかり把握し、自分たちに合ったプランを選ぶことが満足度につながります。
手元供養は安さだけでなく、想いを込めた供養ができることを第一に考えましょう。
本記事で解説した内容を参考に、後悔のない手元供養を実現してください。